| 拵え全体 |
|---|
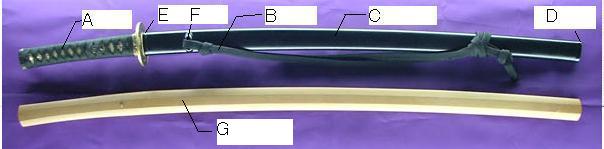 |
A 柄 |
B下げ緒 |
C 鞘 |
D鐺 鞘尻の部分。角製または金属製。
太刀の場合は石突金物と言う。  |
E 鯉口 鞘口、鯉の口に似ている。ほとんど角製。
太刀等で金属製のものは口金物という。  |
F栗形鞘の鯉口近くに付ける角製(ほとんど)。
栗の形をした物。これに下緒を通す。  |
G白柄、白鞘白鞘は休め鞘とも言われ、刀の寝間着のようなものです。
材料は朴(ほお)の木を使います。松や杉と違って、ヤニも少なく加工もしやすく刀にとっては最適なものです。
木は生きているので、時間がたつと延びたり縮んだりします。
これでは精密な作業ができないので、少なくとも10年以上寝かせたものを使うようです。
しかも強制的に乾燥させると後になって湿気を呼ぶので、自然乾燥させます。
|
| 柄 |
|---|
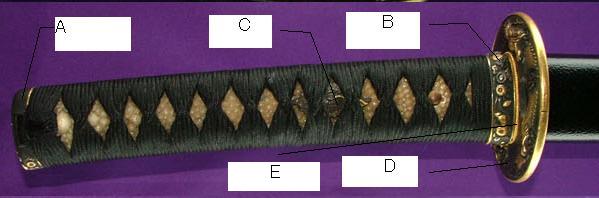 |
A頭 柄の頭を保護する、「縁」と揃い金具の場合が多い。
頭には約1X0.3cmの穴が開いており、ここに柄糸を通す。
この部分の飾り金具を鵐目(しとどめ)という。
金具の場合 くすねで固定する。
古い物(室町後期の打刀)や江戸期においても
正式大小拵では水牛の角頭に柄糸を掛け巻きとするものが多い。
太刀においては冑金となる。  |
B縁 柄口の金具。材質は金、銀、真鍮、赤銅、山金、朧銀、銅、鉄。
これに肉彫等の彫りをする。   |
C目貫刀の柄の一番目立つところに付ける飾り金具。金、赤銅製が多い。
起源は刀身を固定する目釘の頭を装飾した物で、
このような上代の目貫を真目貫(まことめぬき)という。
柄糸を巻かずに完全に露出した物を「出し目貫」という。
 |
D 鍔 手を防御する金具、鐔とも書く。糸巻太刀には葵形鍔が付く。 |
E 切羽 切羽は刀の鍔の表裏、柄と鞘に当たる部分に添える小判型の薄い板金。
切羽がしっかりつまっていると、がたつかない。
糸巻太刀では、表と裏にそれぞれ大切羽1枚、
小切羽が3枚づつ計6枚つく。
 葵形鍔及び大切羽 葵形鍔及び大切羽
 |
 葵形鍔及び大切羽
葵形鍔及び大切羽